沖では10m、家には2m超の津波を経験しました。
東日本大震災からもう少しで15年が経過しようとしています。
あれだけの未曽有の大災害でしたから、まだ最近の様に脳裏に焼き付いているのは確かです。
自分の住んでいる町は2mの津波に襲われた地域です。
数十メートルという地域に比べれば大した事が無いようにも感じるでしょうけれど、ある意味中途半端だからこそ大変な事も多々ありました。
全壊や壊滅とも違った、大規模半壊から復旧というのも修繕を含めて大変な面もあります。
また修繕しても数年後に塩分による不具合が生じたりと、長期にわたって苦しめられたりもします。
まあ、ただ「命あっての物種」という事で、当時は家族全員が助かっただけでも良かったと思うしかありませんでした。
少しでも沿岸沿いを車で走っていたりすれば、かなり危険だった地域でもありますので。
ライフラインの重要性を物凄く感じさせられました。
日常で何気なく使っている「電気」「水道」「ガス」が完全に止まった事は想像できるでしょうか?
当時のライフラインが完全に停止した状況をご説明しましょう。
電気が無い生活
思った以上に多くの物に電気が使われている事を知らされました。
3月というまだ暖房が必要な時期だったので、ファンヒーターを使おうと思っても、灯油があってもファンヒーターは電気が無ければ使えません。
こんな具合に関連している部分に少しだけ電気が必要になるだけで、もうその文明の利器は使えなくなってしまいます。
月の無い夜などは、本当に「漆黒の闇」です。
もうアイマスクを着けて、その中で一生懸命に目を見開いて見ようとしているくらいに何も見えません。
懐中電灯が無ければトイレに行く事もままならない状態です。
懐中電灯、家にありますか?
乾電池も期限が切れていない状態でありますか?
防災グッズはいざという時の為に持っておくのが絶対条件になります。
発電機が倉庫にあっても動かない事が多かったと聞きます。
ずっと使わない状態で倉庫に置いてある発電機は、いざという時に動きません。
大半がキャブレターが詰まっているからです。
大抵の旧型発電機は2サイクルエンジンなので、ガソリンと一緒に混合油を燃焼させて動きます。
月に一度はエンジンを掛けて、最後には燃料の供給を止めた状態でエンストするまで動かして、完全にガソリンも混合油も空にした状態で保管しておかなければ、いざという時に残っていたガソリンが腐っていたり、混合油が固まっていたりして高確率で動かないという事になります。
その為には、最新式の発電方法を装備した発電機や蓄電器を持っておくことを強くおすすめします。
携帯電話等の充電もできなくなります。
当然の事ながら、携帯電話などの充電も不可能となります。
大抵は大地震やそれに伴う津波の被害というのが日本で起こりうる大災害のパターンかと思います。
その他には台風や土石流、火山の噴火などでしょうか。
家族や友人、知り合いの方々の安否が確認できている状態であれば安心ではありますが、まだ連絡が付かない家族や友人がいる場合、どうしても携帯電話が常に繋がる状態になっている必要があります。
東日本大震災当時は、まだガラケーが主流でしたので、いくらかはバッテリーの持ちが良かったという事はありますが、現代では殆どがスマートフォンに代わっています。
つまり、バッテリーの持ちはせいぜい一日というところでしょうか?
多少なりともスマートフォンのバッテリーが劣化している場合、一日も持たないというのが正直なところです。
このスマートフォンのバッテリーに関しては、便利になった反面、当時よりも状況が悪くなった点と言えます。
当然、連絡を待っている側のバッテリーの状態というのもありますが、どこかで足止めを食っている側から家族への連絡も、バッテリー切れでできなくなる可能性もある訳です。
そう考えるとポータブル充電器は必携のものの一つかもしれません。
- 夜は漆黒の闇。本当に何も見えない。
- もし災害が真夏であったら冷蔵庫が使えないので食べ物があっという間に腐ってしまう。
- 充電器、蓄電器の準備が必要。
- ストーブに関しては、電気を必要としない旧式の物を一つは持っていると重宝する。お湯も沸かせるし、ちょっとした調理もできる。
町に少しずつ電気が復旧してきて、周りの家に明かりが点き始めた時に感動は忘れられません。
変電所などの関係で、自分のところはまだでも、遠くの方から明かりが灯っていくのを見た時は、ついに電気が復旧するんだな…と感慨深いものがありました。
水。水道が使えない状況の説明。
電気と一緒に必ず必要になるのが「水」です。
東日本大震災は3月だったので、まだ雪が降ったりする事もあり、発泡スチロールなんかに雪を溜めておくこともできましたが、もしこれが真夏だったりしたら、「水」が無いのは本当に死活問題です。
飲み水だけでなく、水洗トイレも機能しませんし、仮に飯盒などでご飯を炊こうにも水が無ければ不可能です。
当然、風呂に入るなんて夢物語な状態です。
水道が復旧するまでの期間、被害の大きさにもよりますが、直接津波などの被害の無かった地域では1週間くらいで復旧したところもあるものの、直接被害のあった地域は1ヶ月以上も水道が復旧しませんでした。
当然の事ながら、その間は風呂もシャワーも使えません。
身体を拭くくらいなものですが、その身体を拭くにも水が必要になります。
数日に1回くらい給水車が来ますが、一度に貰える水はせいぜい5リットル程度です。
これで数日間、家族で過ごさなければならないのですから大変です。
そのうちに湧き水が出るところに住む方のご好意で、水を配布してもらえたりもしました。
いくらでも出るからと大盤振る舞いして頂きましたが、それで風呂が満タンになったとしても、ガスが無いので風呂には入れません。
仮にプロパンガスのところだったとしても、風呂を炊く為に操作するリモコンに電気が通っていないので無理なのです。
電気に関しても思いましたが、水も完全に断たれるとこんなに不便なんだな~と思わされました。
ある程度は洗濯も必要になってきます。
いくら毎日ではないと言っても、ある程度の期間家族で過ごしていれば、当然の事ながら洗濯は必要になりますし、その際にも必ず水は必要になります。
こうなってくると給水車からもらえる5リットルを「飲み水」に使うか「洗濯」またはトイレを流すのに使うのか?悩ましくなってきます。
とは言っても、水に関しましては多少なりとも給水車が来たりするので、電気ほどの不便さは感じなかったのですが、ただこれが真夏であったならば、飲み水の量も増えますし、調理やその他諸々に必要になってくるので、もっと大変になるでしょう。
ある程度の水を溜めておけるウォーターサーバーは最初の給水車が来るまでの間、心強い味方になります。
ペットボトルの買い置きと併用されればさらに安心です。
災害が真夏であったり、尚の事、小さなお子さんや老人のいるご家庭では、熱中症の危険性も含め水の安定供給は非常に大切なものになります。
最も復旧が遅いライフラインが「ガス」です。
電気や水道が復旧しても、なかなか復旧しないのが「ガス」でした。
恐らく、全てのガス管のチェックが終わらなければ、復旧のゴーサインが出せないのだと思います。
電気と水道が通ってしまえば、オール電化の家庭などでは風呂に入る事が可能になります。
しかし、ガスで風呂を沸かしているところはガスが復旧しない限り、まだ風呂には入れません。
それでも電気さえ通れば調理なども含めてかなりのものが一気にできる様になり、便利になります。
なので、風呂以外は割と何とかなるのですが、何週間も風呂に入れない苦痛は、経験した者にしか分らないと思います。
ガスが通って、久しぶりに風呂に入った時の感動ったら(笑)
これから必ず来ると言われている南海トラフ巨大地震だけではなく、台風や大雨などの被害もいつ来るのか想定できません。
なので日頃から災害時の備えは必要になってきます。
実際に災害が起きた時の不便さと言ったら、恐らく想定しているイメージをはるかに超えてきますので…。
災害時の最初の数日間をクリアできるだけでかなり楽になりますので、この様な防災グッズを備えておくことをお勧めします。
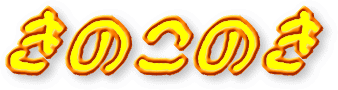

コメント