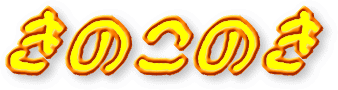ブラックバスが生息しているのなら、そちらを狙いたくなるのは当然の事で。
いつの間にか、東北の沼や湖、川などにもバスが生息する様になってきました。
大手釣り具店が放したという説もありましたが、地中の導水管などを伝って移動して繁殖した可能性もあります。
もう、川などにも入ったら駆除するのは不可能なレベルという事です。
それまで釣っていたライギョも外来種ですし、鯉なども原産としたら国産種ではありません。
昔の食料事情も含めて、色んな理由で持ち込まれてきたのでしょうから、豊かになった今になって問題としても仕方のない部分もあります。
その後に勃発した外来種問題や害魚論など色々と問題視され始めましたが、当時はそんな事は何も言われていない時代でした。
その後のバスブームによって、違法駐車やゴミ問題などが噴出してきて、それに伴って釣り禁止にする理由付けの一つとして、特定外来生物問題やリリース禁止などが言われ始めました。
つまりブームに乗って釣りを始めたマナーの悪い釣り人達によって締め出しが起きた訳で、結局のところ自業自得ってな訳です。
とは言っても、元々の釣り人もマナーが良かったのか?と聞かれれば、特に淡水での釣り人は絶対数が少なく目立たないだけで、決してマナーが良いとは言えませんでした。
ヘラブナを釣っていたヘラ台の周りに練り餌の袋(グルテンマッシュAなどの名前は落ちてたゴミで覚えたw)や吸い殻が散乱している事も多かったですし、海でも、船が岸壁に戻ってくる際にビールの缶を大量に海に捨てている人とかもいましたから。
今では日本人はマナーが良いと言われていますが、それは今だから言える事で、30年前くらいだと、まだまだアジアの国の一つってなレベルだったと思います。
現在、問題視されている来日した中国人の迷惑行動などに関して、当時の日本人も似たようなものでしたね。
まあ、特定外来生物などに関しては、現東京都知事の小池百合子が当時環境大臣だった頃に、リリース禁止を含めて強硬突破で決定してしまった経緯があります。
NBC(日本バスクラブ)や釣り具店、ボート関係の方々が中心となって、反対する署名活動を行うも、本来決められていた期日よりも前に、つまり大量の署名が届く前に
「いいから、もう決めてしまいなさい!」
という鶴の一声で強引に決定してしまった事から、今でも釣り業界、ボート協会からはかなり恨まれ、嫌われていると聞いた事があります。
確かに、その後に倒産したバス関連のショップは多かったので、当然と言えば当然ではあります。
まあ、都知事となった当の本人は、ブラックバス?そんな事もあったね…くらいの感じなのでしょうが。
話は戻ってバス釣りに転向してからの生活は。
何と言っても夢の魚だったブラックバスが近くにいる訳です。
しかも車も持っているので機動力も格段にアップしたので、そこからはもうバス釣り生活三昧です。
しかもバスが入ったばかりのフィールドは、スレ知らずのフレッシュな個体が多いので、もう釣れる釣れる!
バスハンターとピーナッツⅡさえ投げていれば、永遠と釣れるのでは?ってなくらいに釣れました。
サイズは30㎝前後ばかりでしたが。
一時期、あまりに釣れるので飽きて行かなくなったくらいです。
釣るまでの苦労したライギョに比べて、あまりにも簡単に釣れるので、これならいつでもいいや!と思ってしまったのです。
少しバスから離れて、また楽器などを弾いていましたね(笑)
一年くらいのブランクの後に
1シーズンを空けて、久しぶりにバスでも釣ろうか!と気軽に出掛けたものの、世の中ではバスブームが始まりつつあった事も相まって、そう簡単に釣れる環境では無くなりつつありました。
あれ?釣れることは釣れるけど、前の様にいくらでも釣れるって感じではないぞ?
というのが久しぶりにバスフィッシングをした時の感想です。
しかもまだ、トップウォーターとクランクベイトが主流の釣りだったので、攻めと手数にバリエーションが無かったという事もありました。
そして、その後の何回目かの釣行で、初めてのボウズを喰らいます。
あんなに簡単だったと思っていたバスが一匹も釣れなかった…。
負けず嫌いのワタクシは、これでさらに火がつきました!!
そこからは本を読み漁り、トライ&エラーが始まります。
幸い、まだ釣りやすい環境下ではあったので、結果と照らし合わせながらトライ&エラーを繰り返せたのが良かったと思っています。
その時に身に付けた技術が、その後にもかなり役に立ちました。
新しいルアーにも挑戦し始める。
ライギョ時代では使わなかったルアーですが、スピナーベイトやバズベイトのワイヤーベイト。
そしてワーム一式、ラバージグ、ディープクランク(本当の意味でのディープ)、そしてジャークベイトすらメインでは使っていませんでした。
また、トップウォーターと言ってもフロッグ系がメインで、ペンシルベイトやポッパーすら殆ど使ってませんでした。
ペンシルベイトのウィスパー(ダイワ)を見た時などは、リップが無いのにどうやって動かすの?とか思っていたくらいでしたから。
しかも近所の釣り具店にはレッドヘッドのウィスパーだけしか売られておらず、これって海用じゃないの?とか思ってましたね。
その中で、一気にメインルアーに躍り出たのがスピナーベイト。
そんな中、半信半疑で買ってみたのがスピナーベイト。
ボーマー社のブッシュワッカーでした。
当時は500円くらいで売られていた気がします。
この価格もお試しで使ってみるには最高でしたね(笑)
今はもう手持ちは無いのですが、ブレードとワイヤーの付いたヘッドに無造作にスカートがリング状のゴムで止めてあるだけのシンプル構造。
スカートの一本一本が円柱の様な形をしていた気がします。
でも、これがかなり釣れたのです。
しかも40㎝クラスが釣れる確率がやたらと高かったですね。
とは言っても、当時いくら釣っても43㎝くらいがMAXのサイズでした。
恐らく、バスが日本の普通のフィールドで、普通に育つとそのくらいのサイズに落ち着くのかもしれません。
人間の平均身長みたいな感じで。
45㎝を超えてくるとかなり大きく感じました。
その数年後に50㎝を釣った時には55㎝に、55㎝を釣った時には60㎝に見えましたね(笑)
そこから、同じくボーマー社のミニ ワッカー。
ブッシュワッカーのダウンサイジング版です。
とは言っても、パッと見3分の1以下で、かなりのダウンサイズっぷりでしたが。
そして、何と価格は280円くらいでした(笑)
3.5gとベイトリールで投げるには厳しいものがあったので、フックのところにワイヤー状のシンカーを巻いて重くして使っていました。
これは小型も含めて爆釣できるルアーでしたね。
バスブームの真っただ中、ワーミングの人だかりの中でも、一人で爆釣できるくらいの破壊力がありました。
これを水中のウイードや水生植物の枯れた茎などに当て続けると、かなりの数を釣ることができ、スピナーベイトはカバーに当てれば当てるほど釣れると体で覚えさせてもらいました。
根掛かりの回収が難しい陸っぱりから、ロストを恐れずにこれだけ躊躇せずにカバーに当て続けられたのは、280円という金額だったからです(笑)
為替の関係なのか、他に理由があるのか、ブッシュワッカーもミニワッカーも釣具屋から忽然と姿を消したので、その後は代わりになるスピナーベイトを探しまくり、行き着いたのがエバーグリーンのSRミニ 3/8オンスでした。
当時のシークレットとしては、SRミニ3/8オンスのシングルウィローモデルをティアドロップ型の「インディアナ ブレード」に替えて使うのがキモでした。
これは本当に釣れましたね!!
このルアーだけで大小合わせて数百本のバスを釣ったのは間違いありません。
最終的に廃盤になるまで、3つのSRミニがワイヤーの金属疲労で折れるほどでした。
このスピナーベイトの経験を元に、その後、ジャークベイト、ワーム、シャッドそしてトーナメントでは戦略の中心として活躍したラバージグへと、ライギョ時代には使っていなかったルアー達の快進撃が始まるのでした。