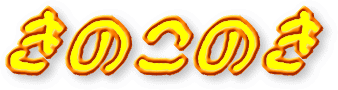花屋を職業としている人が花屋になったパターン。
これまで花を触った経験も無いまま、いきなり花屋(フラワーショップ)を開業した方は、ほぼいないと思われます。
元々、家が花屋だったパターン
まず、花屋になる一番多いパターンとしては、家業が花屋だったというパターンです。
花屋の息子、娘がそのまま家業を継いで花屋になったというケースですね。
子供としても幼い頃から、何となく将来は花屋になるんだろうな…とおぼろげながら思っている場合が多いので、割とすんなり花屋になってしまうという事が言えます。
但し、花屋の息子、娘だからと言って花屋に向いていると決まっている訳でもなく、経営者としての親も、特に叩き上げ系の親は本当の意味での経営を知らないので数字などにも弱い場合が多く、バブル経済に乗っかって上手くやってこれただけというケースも多いです。
これが現在では通用せず低迷しているものの、継いだ後継者に対して
「自分達の頃は、これだけ売った。こんなに儲けた。」
なんて事を言って、自分達の方が上という事を言いたがるので後継者のやる気を削ぐ場合が多いです。
家業が花屋だった場合のメリット
先ずは店舗とそれに伴うインフラが既に整っているという事です。
フラワーキーパーやストッカーだったり、花瓶やバケツなども買ってスタートをする必要がないのが一番のメリットになります。
また、既に固定客が付いていたり、定期の納品先が決まっていたりするのもメリットの一つとして挙げられます。
家業が花屋だった場合のデメリット
何よりも上司のポジションに親や親戚などがいるというケースが殆どです。
元々、親との関係が良い場合、または理解がある親である場合は良いですが、それでも一緒に仕事をするとなると全面的に同じ方向を向き続ける事は、ほぼ不可能な為、どこかでこじれて関係が悪くなる場合も多いです。
また、経営者としての親や親戚、または長年働いている従業員よりも、後継者の方が優秀な場合も苦悩する原因になります。
優秀な後継者は時代に合わせて従来のシステムを合理化していったり、新しいシステムに変えて行こうとしますが、往々にして中高年の人達は変化する事を嫌うので、ここでも対立が起き、後継者は孤立する事も多いです。
また、長年付き合いのある納品先に関しても時代の流れで縮小したり、廃業したりするケースが出てきます。
個人の顧客に関しては、高齢になって施設に入ったり、亡くなってしまい徐々に数が減っていったりもします。
こういった理由により、それまで決まった場所に納品するだけで月々の売上が安定して見込めたものが、少しずつ見込みが立たなくなってきます。
この様な事例に対しても、早い段階で手を打っておけば何とかなったものが、前述のとおり変化を嫌う経営陣や長年勤務している従業員達の反対によって先手を打てないでいた為、現実問題として目の前に突き付けられるまで気付かない場合が殆どです。
こうやって会社が傾き始めたり、借金が膨らんでから社長にされる後継者はたまったものではありません。
さらに、家業が花屋だからといって子供が花が好きかというの、それはまた別問題となります。
花が好きで花屋を始めた創始者と違い、ビジネスと割り切って継いでいるからこそ、業務内容を客観的に見る事ができますし、業界の手間が掛かる割に利益率の低さに嫌気がさしたりするのも、こういった理由からです。
自ら花屋を開業するケース
家業が花屋だったケース以外では、やはり元花屋の従業員、もしくは長い間フラワーデザイン教室に通っていたりして、心機一転、花屋を開業するというパターンが多いです。
製作するスキルは身に付けたので、それを生かして商売としてやっていきたいと思って花屋を始めます。
このパターンは、「花が好き」という前提があるので、顧客さえ付けば、割と長く花屋を続ける事が可能になります。
ここに関しては、家業の跡継ぎのところで書いた「創始者」のポジションにあたり、自分は好きで始めるものの、自分の子や孫が花が好きかどうかは分からないという
また、最初から自分がオーナーとしてやっていくので、仕事に関しては精神的に楽だという事も言えます。
但し、まだ定期購入してくれる顧客や安定した法人顧客が少ないので、自分の力で道なき道を切り開いていかなければならない苦労はあります。
花屋を開業するにあたって必要な経験やスキルは?
一番大切なのは、当たり前と言えば当たり前ですが、花の種類、品種名を覚える事。
そして品種毎に手入れ方法が違うので、それらを全て覚える必要があります。
また、製作に関しても花束やアレンジメントはどんな注文が入っても、即座(15分以内)に作れるくらいの技術を身に付けておく必要性はあります。
特に「花束」は吸水性スポンジ(通称オアシス)で止められるアレンジメントの10倍難しいと思ってもらって良いです。
また、名前やメッセージをカードに印刷したりする必要がある為、サイズの違うメッセージカードや名札への印刷が直ぐにできるくらいのパソコンスキルも必要になってきます。
とにかく買ってきた花を水揚げするにも、手入れするにも、花束やアレンジメント、または生花スタンドなどを製作するにも全てが手作業、ハンドメイドです。
この他にも自分で経営をしていかなければならないので、「簿記」など数字をコントロールするスキルも必要になります。
簿記は絶対に検定を取るとまでは言わないものの、会計ソフトを使って複式簿記を作れるくらいの知識は持っていないとお金の管理がルーズになってしまい、結果的にビジネスを続けられなくなってしまいます。
これらの条件をクリアして、晴れて花屋を開業となります。
自分で開業する場合、店舗の場所を見つけて、前述の条件をクリアして晴れて花屋を開業となります。
今から始めようかな?と思っている方に最初に言っておきますが、花屋の売上総利益(粗利)は40%ほどです。
つまり60%は仕入れ原価になります。
しかも、これはある程度軌道に乗って数年間営業している花屋の数字です。
安定した顧客がいない状態であれば、ロスがさらに増えるので、スタートしたばかりの頃、特に閑散期であれば売上総利益が30%もしくはそれ以下に下がる事も十分に考えられます。
仮に一日10,000円の売上があったとしても、手元に残るのは3,000円という事になるという事です。
当然、その日の分の家賃や光熱費も日割りで掛かっている訳ですから、かなり厳しいのはお分かり頂けるかと思います。
この辺りに関しては「花屋(フラワーショップ)の粗利率」を読んで頂ければと思います。