まず大前提として業種として旬の時期が過ぎていないかどうか?
私自身、自営業を営む家庭に生まれました。
体育大学への推薦をもらうものの、どうせ家業を継ぐことになるからと推薦を断って、高校を卒業して直ぐに家業を継ぐために爺さんが社長をしている会社に入社しました。
まあ、会社と言っても従業員が役員も含めて7〜8人、そこに数名のパートさん達といった零細企業です。
家族と親戚、あとは数名の外部からの社員とパートさん達という構成でした。
入社した時代は1990年。
まだバブル時代が終わりきってはいないけれど、そろそろ怪しいというくらいの時代です。
一応、修行と称して東京で2年弱くらい家業と同じ業種で働いて、その後に戻って今に至るという感じです。
業界的にはバブル期で大きく伸びた業界の一つでしたが、その後の2000年あたりからは、ずっと下り坂という業界です。
それでもまだ、「夢よもう一度」という感じで、年配者も含め今でも事業を継続している経営者達は多いのですが、ピーク時を知っている私から見れば、明らかに斜陽傾向にある業界です。
世の流れに逆らわず、自分の子供達も事業継承の為に会社に入ると言ってくれましたが、少しだけ仕事を経験させた後、よくよく話し合った結果、会社を廃業する事にしました。
現時点での業績自体は決して悪い訳でもなく、付き合いでの借金はあるものの手付かずのまま預金に入っている事実上の「無借金企業」ではありましたがで、業界の将来性を考えた場合にこれ以上の伸びは無いと判断した結果です。
周りからはかなり驚かれ、どうにか続けてほしいという声も多かったのですが、あくまでも長年の暖簾(のれん)を守る事よりも、子供たちの将来の事を考えた末の決断でしたので、気持ちが変わる事もなく、自分でも英断だったと思っています。
経営者の中には人目を気にしたり、暖簾(のれん)を守る事、創業◯◯年に拘る経営者もいます。
しかし、次に経営者になった人が退職するまでに安泰で経営できるくらい余裕がある業界なのかをよく考えて、事業を継承していくかどうかの判断をしていく必要があります。
零細企業にとって、これからはかなり厳しい時代になると思われます。
年々上がる最低賃金、社会保険料、それらをしっかりと支払った上、自分自身がサラリーマンよりも多い所得を得るのは非常に難しい時代になってきています。
現代の零細企業では、社長が誰よりも仕事をして、休み返上で働いた上に給料は社員以下なんてところがゴロゴロあります。
そういった家業としての零細企業は、祖父や父親の時代にピークがあった企業も多く、その後に売上や利益が低下してきて、借金が増えてきたたところで子や孫が事業承継を任せられるといったケースも多くなってきています。
正直、借金が多い状態で会社を、しかもピークは一世代前の業界での会社を盛り上げ直すのは至難の技です。
余裕が無い状態からでは、大胆な政策を打ち出せないから尚更です。
麻雀での戦局を想像してもらうと分かりやすいかもしれません。
祖父や父親が散々振り込み、点棒が10,000点を切った状態で引き継いだとします。
場は半荘で「南場一局」に入ろうとしている段階です。
ここからプラスまで持ち込める確率はどれほどあるでしょうか?
こうやって他の事に置き換えてみると分かりやすい事でも、実際に会社の経営となると五里霧中になってしまいます。
南一局から2翻や、ざんく(30符3翻)で上がってもトータルでは赤字で倒産になります。
しかし残り10,000点でどこまで勝負に出れるでしょうか?
自分が大きな役で上がる為に、強気で通し続けて「跳満」や「親倍満」を振り込んだだけで一撃で倒産してしまいます。
しかもチャンスは自分が親の時の1回のみ。
ここで稼ぎ続ければ可能性はありますが、このチャンスを逃してしまったら、後は運良く何とか大きい役で上がるしか勝つ方法はなくなります。
赤字で、しかも借金もある企業を継ぐというのは、これほどのリスクがあるという事です。
もしもこれから会社を継ぐ後継者であるならば
あまり周りの意見だけに耳を貸さずに、よくよく自分でシミュレートして考える事をお勧めします。
「社長になれるんだから良いじゃない!」
など、自分で社長を経験した事もない人の無責任な意見は結構危険です。
会社であれば、所属している部署、自分の顧客、など狭い範囲での責任になりますが、社長は会社全てに対しての責任になります。
少なくとも社員の倍以上の報酬があるのであればまだ良いですが、同等もしくは社員よりも安いなんてケースもある零細企業では、家族の生活も含めてリスク以外の何物でもなくなります。
割と世の中の人達は、子供が後を継ぐのは当たり前のように考えている人もまだまだ多く、無責任にも事業承継を勧めてくる場合も多いです。
周りの意見に惑わされず、未来のシミュレーションをしっかりと考えた上で決定していく事をお勧めします。
会社の寿命よりも、自分の人生の方がずっと大切ですので。
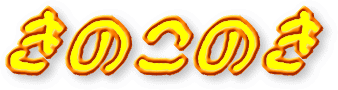
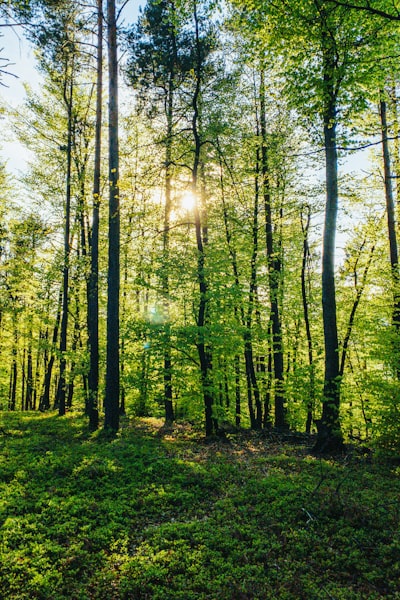
コメント