古来の文化に根差した花
「いけばな」を中心に仏事や神式などで使われる古来からの文化とつながりの多い花ですが、年々その文化が衰退していくと共に使用頻度も下がってきています。
各家庭での仏壇に供える仏花も、昭和の頃の様に神棚の榊と共に毎月1日と15日には花を交換するといった習慣が薄れてきました。
また月命日に花を供えるといった事もほぼ無くなりました。
「盆」の実家へ帰省の際に墓参りをする事はありますが、3月の春彼岸、9月の秋彼岸にもなると実家に帰ってまで墓参りをする事もほぼ無くなっています。
いまだにしっかりと仏壇やお墓に花を供える方もまだ残ってはいますが、こういったものを守っているのも高齢の方を中心とした少数派となってきています。
花屋の商品としては、この仏壇用やお墓用の花が唯一の毎月のサブスクリプション的なポジションであった事から、ここの安定感が揺らぐと、不安定なギフトや誕生日用などに頼らざるを得なくなります。
これでは毎月の基本的な収入が見込めなくなり、同時に仕入れる量の見極めが難しくなってきます。
いけばな業界、フラワーデザイン業界
昭和から平成までは比較的まだ「お稽古」としての花の需要がありました。
「いけばな」の各流派やフラワーデザイン業界などが主流となっている業界です。
そこに少々の茶花などが含まれます。
この「いけばな業界」「フラワーデザイン業界」も共に減少の一途を辿っています。
業界を支えているのが会員であり、この会員の高齢化、そして新たな若年層が入会しないという少子高齢化的な現象が起きています。
それに伴って納品をしていた花屋への注文数も減り、その割に定期的に開催される「展覧会(花展)」などでは、量をさほど使わない割に「特殊な花材」を要求されたりする事でロス率がかなり高くなってくるという問題もあります。
やはり自分で仕入れた物を買ってもらえるのと違い、要求された物を揃えるには、ほどんどが注文品価格によって仕入れ価格も高くなった上、決まったロット数での入荷になる事からロスも発生します。
2本の注文に対して、10本仕入れなければならないといった状況です。
しかし、日頃から納品している業者としては、断る事もできないという厳しい現実もあります。
また出展する先生方も、昔であれば
「金額は気にしないから良い物をお願いしますね!」
という感じでしたが、現在では
「2本だけで良いんだけど、いくらになります?」
といった方が殆どで、2本で良いと言われても花屋は10本以上買わなければならない訳なので、なかなか安くできるはずがありません。
この様に「肩書は先生、買い物は主婦」的な方が多くなってきていて、尚のこと文化に関わる花屋が減ってきています。
1990年代には450万人だった「いけばな」を趣味としている方の人数が、2015年には250万人まで減少したというデータがあります。
そこから10年経過した2025年では、恐らくもうピーク時の半分になっていると思われます。
昔であれば納品業者としての地位が確立できれば、毎日日替わりであるお稽古花の納品によって、固定費としての定期収入が見込めましたが、今では納品する杯数も激減した事から、何とかギリギリの利益で回しているといった状況がほとんどかと思われます。
女性が主体の運営になる事の弊害。
いけばなやフラワーデザイン業界は、99%くらいが女性の会員で占められています。
この部分がどうしても運営上の弊害になってきている面も否めません。
男性に比較して、派閥を作りやすい面もあるので、メインの派閥以外の人達が続けにくくなってしまう環境があります。
また、新陳代謝も遅い事も挙げられます。
女性の方が長寿な事もあって、80代、90代でも現役で先生を続けているといったケースは非常に多く、その下の年齢層の方が「〇〇長」など肩書だけ付けられて雑務をして、実際には裏でその上の年齢層がコントロールしているという、政治家の様な図式が出来上がっている事も多いです。
当の高齢の先生は、自分は何歳でまだ現役だ!という事をステータスにしているので、身を引く事など微塵も考えていません。
こういった中に10代、20代の人達が自ら喜んで入って行くでしょうか?
自分の事よりも業界の事を考えれば、自分が中心となってずっと続けるのか、身を引いて次の世代に任せるのか、どちらが正解かは一目瞭然ではあるのですが、どうしても自分を中心とした近視的な見方をするので、衰退の一途になっている様に思われます。
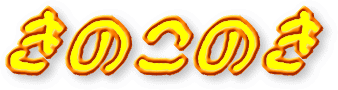

コメント