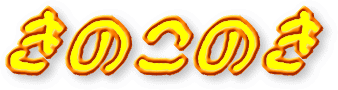ラバージグは徹底的に練習しました。
スピナーベイトに続いて、ライギョ時代には使っていなかった…というよりも、当時の東北では売ってさえいなかったラバージグを、バスに転向した機会に使ってみようと思い立ち練習をする事にしました。
ラバージグは構造がシンプルな割には、市販の物はそこそこの金額がする上、根掛かりし難いとは言えテキサスリグほどのスナッグレス性能も無い事から、陸っぱりからは、なかなか勇気をもってブッシュやカバーに突っ込み切れないでいました。
しかし、ボートを手に入れた今では、カバーにガンガン打ち込めます。
ピッチングの練習と共に、朝から晩までラバージグの葦(アシ)打ちをやって、慢性的な腱鞘炎になるほどに使い倒しました。
メインのフィールドは水深2m以下の沼。
平均の水深が2mですから、当然それよりも浅い場所も多数あります。
ただ1m50㎝くらいの水深でさえ、フォーリングスピードやトレーラー(まあ、これもフォーリングスピードと関わってきますが)によって食い分けてくる事が分かりました。
通常メインとして使っていたのが、ヘッドの重さが3/8オンス(10g)のブラシガード付きのアーキーヘッド、トレーラーはケイテックのカスタムトレーラーの使用率が90%を占めていました。
現在は廃盤で、フレックスチャンクにモデルチェンジした様です。
とにかく、プラスチックワームよりポーク系の方が好きでした。
メインとなるラバージグは、がまかつのコブラ27(3/8 #2/0がメイン)に、自分でラバーを巻いて作っていました。
自作する事で、さらにコスパを上げて、ロストを恐れずにガンガン打ち込むというスタイル。
来る日も来る日もラバージグを使っていると、フォーリング中のバイトや、時折ジグのウエイトが消える様な前アタリなどまで分かる様になってきます。
巻くラバーやブラシガードの「量」や「長さ」も色々と変えて実験していました。
ラバージグ用として使っていたタックルは。
使用していたロッドは、3/8オンスのジグ用に「ノリーズ ロードランナー OUTBACK 630MH」、1/4オンスのジグ用には「メガバス デストロイヤー F3 610X」がメインロッドでした。
リールは、初期の頃はスコーピオン1501、その後はカルカッタ101XT (共にシマノ)を使用していました。
左巻きのリールを使う事で、キャストも操作もフッキングもファイトも全部右手でやっていた事が腱鞘炎の原因でした。
ラインは各メーカーのフロロカーボン14~16ポンド。
ウェッピングやフリッピングの時はナイロンラインの20ポンド以上を使用。
フリッピング用のロッドは、がまかつのラグゼ カマー588(7.6ft)を使ってましたね。
フリッピングの際に左巻きのリールはハンドルが邪魔になる事から、リールはカルカッタ100XT(シマノ)を使っていました。

あれほど好きになれなかったラバージグが、最愛のルアーになり。
自分で制作していた事もあって、ラバージグは溺愛するルアーへと変貌していきました。
根掛かりし難い、投げやすい、フォーリングスピードをコントロールし易い、しっかりとフッキングが決まるとブラシガードがバーブ(返し)の役目をしてバレにくい、などなど使えば使うほど利点が多く感じました。
それまでは結構好きで使っていたテキサスリグの使用頻度が激減した程です。
しかし、テキサスリグの方に分がある時も感じたので、似て非なる存在なのでしょう。
水深が浅いフィールドでのメインは完全にアーキーヘッドのラバージグとなり、その後にフットボールジグをスモールマウス用に多用する様になっていきます。
ソークはした方が良いのか?自分の答えは否でした。
ラバージグを使う際に、発色を良くしたりボリュームを出す為にソークという作業をしたりします。
ベビーオイルや専用のオイルに浸ける事でゴムラバーに油を吸わせるのですが、個人的にはあまり効果を感じていなくて、それよりもソーク後のラバージグを次回使おうとしても、ラバーが伸びた素麺の様にゴワゴワになって綺麗にフレアしなくなったりするのです。
スプレータイプの綺麗にフレアをさせるグッズもありましたが、シリコン製のスカートを巻いた時だけ使っていました。
後は、現場で水中でラバーを揉むだけで、発色は良くなりますし、その後は普通にそのまま使っていました。
時期とフォーリングのタイプによってトレーラーを替える
基本動作としては、フォーリングのタイプはベジテーションカバーに対してフリーフォール。
着底後は、あまりベジテーションカバーから離さない様にシェイキングに近いくらいの、小刻みなボトムバンピング、時折跳ね上げる様に誘って次のスポットへ…という一連の流れが基本でした。
フォーリング中にバイトが集中する日は、ボトムまで落とし切ったら終わりと割り切って、次なるスポットに打ち込む事を優先します。
完全にフリーフォールさせる為に、ベイトリールであればスプールからラインを引き出して、できる限り真下に落とす事は一番意識していました。
当然、ラインを引き出している最中はラインが緩みますから、バイトはラインが水中に入っている部分の動きに集中します。
もはや「浮き釣り」のノリです。
まあ、これはこれでラインが作る引き波に多彩なバイトが出るので面白いのですが。
フリーフォール&ボトムバンピングの時は、ポークかケイテック カスタムトレーラーをトレーラーとして使っていました。
ケイテック カスタムトレーラーが発売される様になってからは、もう面倒くさいポークは使わなくなりましたね。
それほどまでにケイテック カスタムトレーラーは素晴らしい商品でした。
ケイテックの商品は、林 圭一さんの性格がそのまま商品化された様な繊細な商品ラインナップで、また雑誌で解説されていた林さんのフリッピング理論なども、とても勉強になりました。
林さんのご冥福をお祈り申し上げます。
秋口になってきた頃には、割と横へ移動するものに対しての反応が良くなってきますので、トレーラーをグラブやカーリーテールなどに変えて、カーブフォールで誘うと反応が良い時が多くなります。
流石にカーリーテールは通し刺しでトレーラーにしていましたが、グラブに関してはチョン掛けで使う事が多かったですね。
チョン掛けする事で、左右への動きも加わって、実際に反応が良くなる気がしていました。
キャストで着水させたら、ラインがあまり緩み過ぎない程度にロッドティップをキープしつつ、フォールスピードよりは、緩やかにティップを下げる事で手前にスイミングさせてきます。
するとラインが突然横に走るように動くバイトが出たりしますので、焦らずにその走ったラインと逆方向へフッキングします。
また、ストンッ!と速いフォーリングに反応が良い時もあります。
そんな時は1/2オンスのジグにZOOM(現ZBC)のミートヘッドや、エバーグリーンのフラットヘッドミノー マッチョの様なストレート系ワームをトレーラーにして、できるだけ垂直に速く落とし、着底後のスカートのフレアとストレートワームのプルッとした動きで誘っていました。
ラバージグのフッキング
ラバージグはキチンとフッキングできれば、特にブラシガード付きは、かなりバレにくいルアーではあるのですが、どちらかというとフッキングまでの過程が重要になります。
ワーミング同様にバイトの出方も千差万別なので、先ずは数あるバイトの出方を経験されるのが早道ではあります。
それには、多少なりとも使い込む時期が必要になってはきます。
ブラシガード付きラバージグのフッキング。
ブラシガード付きのラバージグのフッキングですが、突然「ゴンッ!」というバイトも多いので、つい反射的に合わせてしまいがちです。
しかし、「バシッ!!」というフッキングでは、ラインスラッグ分が張るだけで力が伝わらず、意外にしっかりと針が貫通していない事も多いのです。
特にバンピングでロッドティップが45度くらいまで上がってきている状態からでは顕著になります。
そこからのフッキングでは、針先が乗っかる様に少し刺さっているだけで、1発のエラ洗いで外されてしまう事が多くなります。
ラバージグはワームの各リグに比べて、着底姿勢が安定している事から、フックが上を向いている事が多く、完全なる真芯にフッキングが決まると、目の間の一番硬い部分にフッキングする確率が高いです。
硬いという事は、しっかりフッキングできると外すのに苦労するくらいにガッチリ掛かるのですが、そこに貫通させるにもパワーが必要になるという事です。
ラバージグは、その複雑な感触からか、バイトからルアーを吐き出すまでの時間が長い様に感じます。
なので、バイトがあったら焦らずにしっかりとロッドティップを水面側に戻すようにしながら、その緩んだ分のラインを巻き取り、フッキングストロークをしっかり確保してから、長く強くスイープに合わせるのがベストです。
フットボールタイプのラバージグのフッキング
フットボールタイプのラバージグは、ブラシガードが付いていない分フッキング率は上がります。
但し、ヘッドが重い分、ジャンプと同時にエラ洗いされたりした際に、フッキングした部分を支点としてヘッドのおもりが振り回されてバレる確率が上がります。
なので、フッキング率が高い事を利用して、フットボールタイプのラバージグは、一気にフッキングしたら高速でリールを巻き取り、仮にそのまま空中で外れたとしても、ボートの上に収まる様に一気に抜き上げてくるのが良いです。
ファイト時間が長ければ長いほど、口の柔らかい部分に掛かっていた場合、貫通した穴が大きくなってバレやすくなってしまいます。
ただ、ガード付き同様、真芯の硬い部分に刺されば外すのが苦労するくらいにしっかりとフッキングします。
スモールマウスなどでは、口が小さい分、なかなか外せなかったりもする程です。
ラバージグの使い分け
ガード付きタイプ
当然の事ながら、ガード付きラバージグの場合はベジテーションカバーを中心にカバーを狙って打ち込んでいくスタイルに合っています。
ヘッドもアーキーヘッド(先細のコブラ型)なので、カバーの間にもすり抜けて入って行きやすい形状になっています。
オープンウォーターでも使用は可能なので、ある意味万能とは言えます。
フットボールタイプ
フットボールタイプのラバージグは、横長で楕円またはアーモンド状のヘッドなので着底姿勢が安定し、フックとトレーラーが常に上を向きやすいという利点があります。
また、初期フッキングの良さもガード付きラバージグに勝る点です。
オープンウォーターのブレイクラインをボトムバンピングさせたり、水中のハンプなどを攻める際にはその安定感により誘いやすくなります。
またフォーリング時の姿勢もアーキーヘッドに比べて安定しています。
トレーラー
ラバージグは、単体で使用する事はほとんどありません。
単体でも釣れない事はないのでしょうが、基本的にはトレーラーを付けて使用します。
トレーラーの種類を紹介します。
ポーク
昔は低水温期の定番はポークでした。
低水温でもテロテロした動きとフォーリングをよりスローにする浮力と抵抗。
バイト時間が長くなる…などなど、低水温期の利点が多かったのです。
それから、グラブなどをトレーラーにした際の、テイルがベジテーションカバーに絡みついて落ちて行かない…などのトラブルも皆無です。
ただ、保管が面倒くさいのと、夏場に使うと劣化しやすいというのが難点です。
ポーク系の動きを再現した、専用トレーラー。
過去にはケイテック カスタムトレーラーが発売されて、一気にポークを使う機会が減ったという現実があります。
やはり管理が楽なのと、手がデロデロにならないのは最高でした。
ただ、素材の関係から通常のプラスチックワームとくっ付くと溶けてしまうという欠点はありましたが。
今も名前と形を変えて進化しているので、十分にポークの代用として使えるでしょう。
各形状のプラスチックワーム
ギドバグなどのクローワームをセットしたものの紹介が過去には多かったのですが、個人的にはあまりクロー系のワームをトレーラーとして使ってはいませんでした。
しいて言うならば、ホッグ系の方を多用していました。
多用と言っても、大半はカスタムトレーラーで事足りていたのですが。
あとはフォーリング重視でグラブやツインテールグラブ、速い落とし込みでストレートワーム、ボトムバンピングで時々パドルテールを使っていたくらいでしょうか。
秋口にはロングカーリーテールが、カーブフォールにて強烈に効く時期がスポット的にありました。
溺愛していたラバージグというルアーをまとめてみると
一言で言えば万能ルアーです。
スピナーベイト的にも使えますし、ワームとしても使えます。
重さで投げやすい反面、ラバーとトレーラーの抵抗でフォーリングスピードを抑えられるので、ベイトタックルでパワーフィッシングながら、フィネスな攻めが可能になります。
ルアーを一つだけ持って行けと言われたら、持ち込むルアーの筆頭に上がるでしょう。
万能な反面、自分からはスカートを開く以外何もアクションをしないので、使い手次第で爆釣ルアーにもダメルアーにもなります。
そのあたりが、ラバージグを好きな人と嫌いな人の分かれ目になるかと思われます。
ただ一点だけ書いておくとすれば。
滅多にないですが、ごくごく稀にラバージグが全く釣れないフィールドがあるのも確かなのです。
ベイトの種類なのか理由は分かりませんが、明らかにラバージグが効かないと感じるフィールドがあったのは確かです。
これに関しては頭の片隅に残しておいて良いと思います。