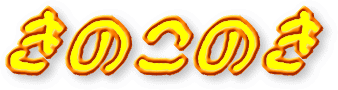第二次バスブームの際には、にわか雑誌も多く、全ての障害物をストラクチャーと呼んでいました。
「ブラックバスは、障害物を好む傾向にある魚なので、ストラクチャー(障害物)を積極的に攻めましょう!」
当時よく書かれたり、言われたりしていた事に一つに「ストラクチャー(障害物)」というものがあり、たしかにそれだけ読むと、障害物をストラクチャーと言うのか!なるほど!と思いますし、また雑誌などでストラクチャーという言葉を覚えた人によって積極的に使われ出し、一般のアングラー達に広まっていった経緯があります。
当然、ワタクシも雑誌等で「ストラクチャー(障害物)」を知り、一時的には納得したものです。
そのうちに、「カバーやストラクチャー」などという言葉も出てくる様になり、段々と線引きが曖昧になってきました。
「ヘビーカバーにはフロッグ」とか書かれていると、水面を多い尽くす状態のストラクチャーはカバーというのか?とか、少し難解になってきていましたね。
そんな時にワタクシの心の師匠「ヒロ内藤さん」が、地形的な変化がストラクチャーと明言。
当時はバス業界の広告塔となっていた村田 基さんや、オールドバスプロに加えて、新しいトーナメントプロなどが台頭してきており、雑誌を賑わせていました。
しかし、今思うに当時の日本の「バスフィッシング」への理解度は浅く、雑誌などに登場するプロは、要は他より釣るのが上手い「釣り名人」という範疇であったのは否めません。
今ほど情報も無かった時代でしたので、何かコツを知っているだけでも割と上位に行ける時代ではありました。
そんな売り出し中の華々しいプロ達に比べ、本場アメリカのバスフィッシングを身近で見て、取材して身に付けた「知識と技術」が超一流の「ヒロ内藤さん」は、その控えめな佇まいと地味な(失礼…)雰囲気で、それほど雑誌に登場する回数は多くはありませんでした。
ただ、ワタクシが一番読み込んだ本が「ヒロ内藤 ハイパーバッシング」で、その後にずっとワタクシのバイブルとなっていたので、ヒロ内藤さんが登場した回の雑誌は穴の開くほど読み込んでいたのです。
そのヒロ内藤さんが
「ストラクチャーとは地形的変化の事を指します。」
と言い切ってくれた事で、自分の中のモヤモヤが晴れました。
ストラクチャー
ストラクチャーとは天然の地形的変化。
すなわち、ボトム(底)、切り立った水中の壁、岬、チャネル(水路状のボトム)、ブレイク(かけあがり)、ハンプ(こぶ状の盛り上がり)などがストラクチャーになります。
特殊な例としては、人工物の護岸やテトラポット、漁礁などが、人工的な地形変化の意味で「マンメイドストラクチャー」と呼ばれます。
カバー
ストラクチャーに対して、岩、石、ベジテーション(水生植物)、立ち木、桟橋など、ストラクチャー以外の障害物をカバーと呼びます。
このストラクチャーとカバーの違いを理解する事で、それらを複合した攻めが可能になります。
これを理解してから、その後に雑誌等の記事で「読む価値」があるかどうかの判断として、そのプロがカバーをストラクチャーと呼んでいたら、そのプロの記事は読まないと決めました。
こうやって考えてみると、当時として結構な大御所のプロもこの辺りをごちゃ混ぜにしているのが分かりました。
ストラクチャーとカバーの違いを利用した攻め方
考え方としては、水深2m~4mのブレイク(かけあがり)があったと仮定します。
その3mの位置でバイトがあった場合、その日のレンジは3mの可能性が出てきます。
もし魚群探知機などを持っていれば、そのバイトのあった地点をチェックして、何も無かった場合はレンジそのものがサーモクライン(水温変化層)などの影響で3mである可能性が高くなり、その3mの位置に岩などがあったら、レンジよりもそのカバー自体に付いていた可能性も出てきます。
ストラクチャー優先の場合
バイトのあった地点の水中にカバーが無い場合、先ほどの例で言えば水深3mですが、その3mのレンジでブレイクとぶつかったエリアを先ずは重点的に攻めていきます。
他のレンジを捨てて考える事で、効率的なルアーも選択できるので、攻めの効率が高まります。
カバー優先の場合
3mのレンジでの岩でバイトがあった場合、カバー中心の考え方としては、そのカバーの「マテリアル」を考えます。
岩であればロック系の硬めのカバーを意識します。
もしストラクチャー優先で狙うべきレンジ(水深)が明確になっている場合は、そのレンジと重なる水深に絡んだ硬めのカバーを狙うと決め打ちしていきます。
これで、
①水深3m ②硬いマテリアルのカバー
という2つの要素が明確になります。
そうなると、水深3mのハードカバーを狙うには「ラバージグ」や「テキサスリグ」でバーティカルに攻めるなどと、効率が良くトラブルの少ないチョイスが自ずと出来てきます。
さらに細かい部分では、攻める物が岩なので根掛かりの確率が少し低い事から、ラバージグはフッキングを重視してフットボールジグを使うか?などと展開していきます。
カバーのマテリアル
前述の通りに、カバーには大きく分けて、3種類のカバーがあります。
それによって使用するルアーをチョイスする事で効率の良い攻めが可能になります。
①ハードカバー(岩や石等)
基本的にバスは硬い物が好きで付く傾向があります。
石や岩が続くエリアでは、クランクベイト、スピナーベイトなどをボトムや岩に当てながら引くことで線の攻めが可能になり、またバイトの出る水深やカバーが明確になれば、ラバージグやワームの各リグで点の攻めへと展開できます。
根掛かりは岩や石の間にルアーが挟まる事がほとんどなので、その点を注意したチョイスが必要になります。
②ウッドカバー(立ち木や杭など)
ウッドカバーも時期によっては好んで付くカバーになります。
バーティカル(垂直)に落とし込んだり、レンジが分かっていれば、そのレンジで横にコンタクトさせたりと多彩な攻めが可能です。
やや、根掛かりが増えますので、スナッグレス性能の高いルアーが使いやすくなります。
ガード付きのラバージグやテキサスリグ、スピナーベイトなどが使いやすいですが、ボートからの釣りで回収が可能であれば、同じ水深を確実に通せるクランクベイトをコンタクトさせるのも効果的です。
③ベジテーションカバー(葦、ガマ、フトイ等)
水生植物で構成されるカバーをベジテーションカバーとして考えます。
夏場などは葦(アシ)打ちなどが効果的になります。
ベジテーションカバーは中に入り込むスペースがあるので、天然のシェードが生まれますし、特に葦などであれば多少水通しが良いエリアでもあるので、シェードと水通しという複合カバーになります。
葦に比べて、フトイやガマなどは水通しの悪いエリアが多いので、春先の水温が低い時などはこちらが優勢だったりもします。
使うルアーは、テキサスリグ、ラバージグを中心に考え、カバーの奥なのか手前なのかでシンカーの重さや使うリグを設定していきます。
ベジテーションカバーエリアは水深が浅い事が多いですが、それでもバイトは、フォーリング中なのかボトムに着いてからなのかハッキリと分かる事が多いです。
フォーリング中なら軽めにしてフォールの時間を稼いだり、ボトムであれば重くして早めに落とすなどの工夫で、より効率の良い攻めが可能になります。
リリーパッド
水面を覆いつくす「菱藻(ヒシモ)」や「蓮」などに対しては、フロッグやノーシンカーリグでリリーパッドの上を、中は重いテキサスリグなどをペグ止め(ウキ止めゴム等でシンカーを固定)するか、ねじ込み式のフロリダリグを使ってバーティカルに攻めます。
バーティカルな攻めに関しては、基本ボートからの釣りになります。
以上が自分なりの解釈でこれまで実践してきた、バスフィッシングにおいての「ストラクチャー」と「カバー」の使い分けになります。
ここを切り離して考える事で、さらに多くの組み合わせの引き出しが生まれ、これを読んだ読者の皆様がよりたくさん釣る事ができたら嬉しい限りです。